世界はニッチな研究でできている。
そう思ってしまうような研究がたくさんあった。
でも確かに一般的にはメジャーなジャンルと言われるような専攻でも、
突き詰めて学んでいけば、やがて壁にたどり着き、
やがて壁を破ってニッチになるんだろうな。
色んなジャンルに触れられており、
さも世界の壁の少し先を知ったような気になれた。
内容とは関係ないことで失礼は承知だが、
寒冷地での物の壊れ方を研究されている教授のお名前が
トュックリ先生という方で、饅頭フェイスの機械音声で
「ゆっくり聴講していってね」って言いそうとか思ってしまった。
研究内容は非常に有意義で素晴らしいことだけに、勝手ながら誠に申し訳ない。
個人的に一番気になった項目は、三重大学の忍者の研究だ。
忍殺を読んでいるニンジャヘッズとしては、この内容があったから本書を
手に取ったといっても過言ではない。
とはいえ、一応いい大人の端くれなので、
忍者に過度なファンタジーを求めている訳ではない。
それでも自分の内に持っていた忍者のイメージが変わる内容だった。
忍者と言えば、小集団で活動して技やスキルで諜報活動や暗殺をする
ストイックなダークヒーローというイメージを持っていた。
しかし、本書内でも引用されていた『万川集海』という忍術書によれば、
忍者は正しい心を持たねばならず、正しい心とはすなわち仁義忠信を守ること。
正しい心は本人だけでなく、妻子や親族も持つべきである。
陰謀や騙しは忍者として良くない姿で、
私欲のために忍術を使うのは盗人と同じだ。
そして平素柔和で、義理に厚く、欲が少なく、理学を好んで、行いが正しく、
恩を忘れないことが忍びとして必要な要素である、と。
いや、忍者に求められるハードル高いな!
そりゃ忍者という属性の人たちが皆そうだった訳じゃないだろうけど、
もっと孤高の隠密戦闘者と思っていた。
忍者の正しいイメージが伝わってこなかったことも、今この現代において
忍者研究が必要な理由だろう。
忍者は基本的に誰かに仕えて、磨き上げた技を振るう存在であり、その秘匿性は高い。
その秘匿性の高さ故に、一家に伝わる技をみだりに他者に伝えることはなく、
営々とその家系で技が秘匿されていた。
そして現代になって、家にこんな書物が残っていました、という形で研究資料が提供されることで、正しい忍者のあり方が分かってきたということだ。
自分をいい大人だと自称したが、やはり男の子にとって忍者は1つの憧れだろう。
ならば、分かった事実をもとに自分の忍者イメージもアップデートが必要だろう。
話を本書に戻すと、他にも興味深い研究が全19選紹介されている。
ガッツリ深くとは言わないが、新たな知見を得られる良書だと感じた。
ぜひ読んでみてほしい。
そして、それはそれとして忍殺は忍殺でその一見トンチキな内容を
いちヘッズとして楽しんでいこう。

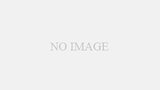
コメント